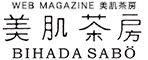Q:日本語には「茶」が使われている言葉が多いですが、それはなぜ?
A:昔から日本人はお茶を飲み続けてきました。単なる水分補給ではなく喫茶文化をも形成してきました。「茶」という言葉が今も残るのは、生活文化に深く浸透していることの証しです。

これまで「お茶の基本(入門編)」として、身近だけどあまり知られていないお茶に関する知識を取り上げてきました。最終回の今回はまとめとして、日本語のお茶に関する言葉を幾つかピックアップし、実は思っている以上に広く深く私たちの暮らしにお茶が浸透していることをご紹介します。
作法
子どもの頃、食事のときに次の言葉とともに作法を注意されたことはありませんか。
茶碗に箸を立てると人が死ぬ
仏教のお葬式ではご飯にお箸を立てて死者に供えるところから、普段は茶碗のご飯にお箸を立てるのを忌み嫌います。
茶碗を箸で叩くと貧乏神がくる
茶碗をお箸で叩くのは行儀の悪いこと。貧乏神を引き合いに出した、しつけのための戒めです。
健康・幸運
昔から、朝にお茶を飲むことは健康によいとされてきました。また、災難除けや幸運とも結び付けられています。
朝茶に別れるな
朝茶の習慣はやめないようにとのストレートな言葉。
朝茶はその日の難逃れ
難は厄介ごとのことです。朝茶を飲めばその日は面倒が起きないという意味。
朝茶は福が増す
朝茶を飲めばその日の幸せを増やすという意味。
お茶の味と木
お茶の味や木に関する、どれも知っておくとよい知識的な言葉もあります。先人の経験則から生まれた言葉です。

宵越しの茶は飲むな
お茶は淹れたての美味しいうちに飲みなさいという意味。時間が経ったお茶は、成分が変質して身体にもよくありません。
良い茶の飲み置き
よいお茶を飲むと、いつまでもその味や香りが口の中に残ること。
茶の木を植えると死人が出る
茶の木は植え替えを嫌うので、成木を植えるより種子を植えなさい、という意味。
茶の花が上向きに咲くと雪が少ない
茶の花は雪の季節と隣り合わせ。気象の経験則から生まれた言葉で、新潟、福井、島根、広島、山口、熊本などの県で言われます。
高価なお茶
貴重なお茶をたくさん飲ませないために使われていた、ウソも方便の言葉もたくさんあります。現代で使われることはありませんが、これらの言葉をみると、昔はお茶がどれだけ貴重なものだったのかが想像できます。
茶を飲むと色が黒くなる
茶を飲むと早く年をとる
お茶を飲むと目が悪くなる
その他
実際によく聞く、言ったことがある「茶」のつく言葉を集めました。言葉の意味をきちんとと理解していましたか。改めて確認してみてください。

鬼も十八、番茶も出花
誰でも一生に一度は美しい時期があることの例え。
お茶の子さいさい
茶の子は簡単な食事のことで、“さいさい”はハヤシ言葉。物事がたやすくできること。
茶々をいれる
お茶をおいしく淹れるには適度の分量があるので、茶に茶を加えると台無しになります。茶々には妨害、無分別の意味もあり、話の本筋から離れたひやかしを入れて妨げること。
茶柱が立つと縁起がよい
茶葉の中に混じった茎が、淹れたお茶の中で立つこと。茶柱が立つことはめったにないので、人に話さなければよいことがあるという縁起かつぎ。
へそで茶を沸かす
おかしくてたまらないことの例え。また、聞くだけばかばかしいこと。
日常茶飯事
お茶やご飯は日常に根ざした珍しくもないものなので、ありふれた平凡なこと。
新訂 緑茶の事典(髙野實・谷本陽蔵・富田勲・中川致之・岩浅潔・寺本益英・山田新市 執筆、日本茶業中央会 監修/柴田書店 発行)